サラリーマンは、二度会社を辞める。
読了したので要約していきます。
サラリーマン人生を送るにあたっての処世術みたいなのが書かれてます。
これも目から鱗の素晴らしい内容です。
個人的に刺さった箇所を抜粋して簡単な私見を述べていきます。
それでは見ていきましょう( ´ ▽ ` )ノ
自分に向く仕事は、他人が決める
若手社員がすぐに好きな仕事に出会い、自分らしさを発揮しながら会社の業績に直接貢献できることはありえない。
本書抜粋引用
配属を決める人事部も本人の適正など十分にはわかっていないのである。
また、自分の得意なことや好きなことは、自分ひとりで思っているだけでは見聞が違うことが多い。
自分の能力や仕事ぶりを判断して評価するのは、あくまでも他人なのである。
これは林修先生のいっていた内容と全く同じですね!!!
自分の好きなこと/やりたいことが、必ずしも他人から評価されるわけではないし
逆に自分ではやりたくないけど、自分の能力が他人に評価されることもあるわけで。
林修先生の執筆した本でヒット作は自己啓発本ばかりです。
これは林先生曰く、別に書きたくて書いたわけではないとのこと。
逆に林先生自身が書きたいと思った本は「寿司・うなぎ・天ぷら」でこれは執筆したけど、全然売れなかったそうです。
初耳額で公開された熱血教室~高学歴ニート編~で
塾講師も元々やりたかったわけじゃないけど
たまたまヘルプで家庭教師とか塾講師入ったら全部で評判がよかったため
アルバイトでやっていたというお話です。
これはまさに自分でやりたかったわけじゃないけど
他人から評価されたという典型的なエピソードですね。
以前、書いた記事もぜひ参考に!!!
ほとんどの人は、スティーブジョブズにはなれない
マスコミが取り上げる若手起業家やコンサルタントなどに憧れて、自らを彼らに重ね合わせようとする若手社員もいる。しかし、彼の主張が自分の胸に突き刺さることと、自分が彼になれることの間には格差がある。
成功者を短期的な目標にした場合、自分に合う本当の道があると思い込み、ますます、日常の職場に充足感が持てなくなりがち。日々の仕事に身が入らず、周囲の仲間からの信頼を失うことにもつながりかねない
そもそもスティーブ・ジョブズ氏のように若くして起業家になれる適性を持っている人はごくごく少数
本書抜粋引用
そう、これは本当にそう。
起業家、Youtuber、プロスポーツ選手、アーティストでも、自分の才能を信じて疑わず、それを活かして世の中にvalueを生み出している人たちは
ほぼほぼ、みーんな若いころから自分のやりたいこと見つけて取り組んでいる。と僕は思います。
お笑い芸人とか演技役者だと遅咲きのパターンあるかもだけど(;´∀`)
30過ぎで起業して成功した三木谷さんみたいな人もいるかもだけど
三木谷さんはそもそもがエリートだし、やはり圧倒的少数派かと。
まぁ、年齢が大事とかそういうわけではなく
マインドセットとして、適性ある人はやはり若いうちから自分で道を切り開いてるということですな。
就職してサラリーマンになろうと思う時点で、よくも悪くも凡人ですね。ただし
- 凡人だから幸せじゃないとか
- 凡人だからダメとか
- 凡人だから夢を諦めるとかそんな必要はなく
まずは現実を受け入れ、そこからどう行動していくかが重要ということなんでしょう!
会社では頑張ったぶんは自分には返ってこない
取材をうけた際に記者に
本書抜粋引用
「若い理系社員の中には「大学時代には、毎日実験もあってよく勉強してきたのに、会社に入るといつも遊んでいた文系の学生のほうが出世して彼らにこき使われる。これは納得がいかない」と発言する人がいる」と言われた。
私は記者に「そもそも、自分は勉強してきたのに、と考えること自体がおかしい。会社は1つのコミュニティーなので自分が努力した成果がそのまま自分に戻ってくる仕組みになっていない。その代わり、自分がしんどい時は周囲から助けてもらえるケースもある、それが会社です」とコメントした。
受験では頑張った分がそのまま自分に返ってくるが会社内ではそうではないと、組織で働くとは?について考えながら説いています。
ここのエピソードは、かなり刺さるものがあるのでぜひ本を手にとって読んで頂きたいです。
会社は給料をくれるだけではない→会社人間になってみる。仕事の不満は仕事で解決せよ。
若い人がすぐに外で勝負することは難しい。経験の差は時間で埋めるしかない。
組織での仕事は、誰もができることをベースに設計されているので、若い時にまず自分を鍛えるには格好の舞台となりやすいのである。たしかに「会社の仕事は収入を得るため」と割り切る考え方もあるだろう。しかし時間と労力を考えると、仕事とは全く別の何かに取り組むのは、現実的には難しい。若いうちは日常の仕事から何かを学び取る方がうまくいくことが多い。加えて、立場や考え方の異なる仲間と一緒に働くことは会社を離れてなかなか得られない経験なのだ
本節では趣味は趣味でしかなく、仕事は世の中の多くの人に必要されていると説いています。
納得できない指示を受けたり、厳しい叱咤もあるかもしれないけど、それが社会の1コマであり、その中で働く意味を見つける、それが大人になるということではないかとの
意見が述べられています。
まぁ、昨今はパワハラ、モラハラなどなど、ハラスメントに対し、より厳しくなっていますからね。
ここらへんの指導とハラスメントの境界は中々難しい気もしますが。。。。
本節では一度組織とどっぷりと格闘しないといけないと説いてますが、ブラック企業で一生懸命働いても搾取されるだけでなくメンタルもやられるので
本当に組織と向き合い、仕事と向き合うのが「正」なのかは考える必要あるように見えます。
ただ、やはり目の前の仕事に一生懸命に取り組むというスタンスは、それはそれで大事なポイントのようです。
岩瀬大輔さんのブログにも似たような書かれてたしね。
仕事は向こうからやってくる
人との偶然の出会いによって次のステップが見えてきたという人が大半。キャリアや自己実現は自分で探すというよりも、むしろ向こうから呼んでもらうもの。仕事というものは、自分がするのではなくて、いろいろな縁や出会いの中で他人からさせてもらっている。やはりキャリアの展開は他人からの要請で進んでいくもの
これはもう1で述べた林修先生のエピソードと駄々被りですよね^^
ええ、これはもう真理なのでしょう。
やはり、同じ会社の人とだけ仲良くするとか頻繁に飲み会するのは良くないなと思いました。
色んなコミュニティに顔を出し、可能性を探っていくのがよいのではないでしょうか。
同じコミュニティの人とのつながりも大事だとは思いますが、思考プロセスとか考え方とか偏るしね(;´Д`)
誰のために働くのか?
このセクションでは、何のために、誰のために働くのか?を学生とディスカッションしたら
①お金を稼ぐ②自己実現・自己成長の2つに大分類できたというところから話が始まります。
上述の通り、会社を通じて自己実現を成し遂げようとすべきではない!
目の前の仕事に全集中常駐しなさいといった趣旨を
欧米と日本の文化的な違いや、目の前の仕事に取り組む姿勢に言及しながら述べています。
総括
読み物としてかなり面白いですし、いいこと書いてあるので
退職、転職を考えている人にはもちろんのこと
サラリーマン人生について思うことがある人はぜひ一度手に取って読んでみて欲しいです。
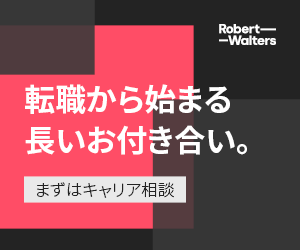








コメント