ども、爽太です。金利が日常生活に影響するのか?備忘用に記事を残しておきます。
金利がある世界って?今の日本、どう変わってるの?
最近、「日本も金利がある時代になった」なんて話、聞いたことありませんか?
これ、実は私たちの生活や投資にけっこう関わってくるんです。
まず「金利」ってなにかというと、かんたんに言えば「お金を借りたときに上乗せして返す分」のこと。たとえば、100万円借りて年利1%なら、1年後に101万円返す、みたいなイメージですね。
「金利がある世界」ってちょっと難しく聞こえますが、ざっくり言うと「これからはお金の貸し借りにちゃんと“利子”がつく時代になる」ってことなんです。
この金利、実は投資信託にも大きな影響があるんです。たとえば債券型の投資信託って、金利が上がると価格が下がるし、金利が下がると価格が上がるという関係になってます。
↑金利が上がる
↓債券の価格は下がる
(反対に、金利が下がると債券の価格は上がる)
だから、金利の動きによって運用成績が大きく変わってくるんですね。
株式型の投資信託も、金利や景気の動きに連動することがあるので、まったく無関係ってわけではありません。
なんで今、金利が上がってきたの?
実は日本って、1999年から「ゼロ金利」、2016年からは「マイナス金利」っていう、ほぼお金を借りても利息がつかないような時代が長く続いてたんです。
それが最近、日銀(日本銀行)が「そろそろ金利を上げていこう」って動き始めました。なんでかっていうと、物価や経済のバランスを整えるためなんですね。
金利が下がる → お金を借りやすくなる → 消費・投資が増える → 景気が良くなる
金利が上がる → お金を借りにくくなる → 消費・投資が減る → 景気が落ち着く
日銀はこうやって金利を調整して、「景気が暴走しすぎないように」「逆に冷え込みすぎないように」バランスを取ってるんです。
物価が安定してるって、そんなに大事?
たとえばスーパーで「今週はトマトが安いな~」って思って買うこと、ありますよね。これ、私たちが自然に物価の変動をチェックしてる例です。
企業も同じで、値段の変化を見て、「あ、これは人気ありそうだ」とか、「売れないな」とか判断して、生産や投資を決めてるんです。
でも、物価が上がりすぎたり下がりすぎたりすると、「何が本当に売れてるのか」が見えなくなって、経済がうまく回らなくなる。だから日銀は、金利を調整して、物価が安定するようにしてるんです。
「物価が安定する」=「消費や投資が安心してできる」ってことなんです。
企業も、材料費や人件費の見通しが立たないと、投資や採用に慎重になります。
でも、物価が落ち着いていれば、みんな安心してお金を使えるんです。
これが経済を回すために超重要。
日銀って、どうやって金利を調整してるの?
ここがポイントなんですが、日銀は「オペレーション」っていうやり方でお金の流れを調整してます。
大きく分けて2つあって:
- 資金供給オペレーション:世の中にお金を多く流して、金利を下げるやり方。
- 資金吸収オペレーション:逆にお金の量を減らして、金利を上げるやり方。
たとえば景気が悪いとき、金利を下げれば企業や個人がお金を借りやすくなるので、投資や消費が活発になります。逆に景気が良すぎて物価が上がりすぎてるときは、金利を上げてブレーキをかけるんです。
日銀が利上げ → 銀行の貸出金利も上がる
→ 住宅ローンの返済負担が増える
→ 投資信託の運用成績が変わる
→ 株価が動く
→ 投資銘柄の選び方にも影響!
最近の動きってどうなってるの?
2024年3月、日銀はマイナス金利をやめて、なんと17年ぶりに利上げしました!さらに7月にも追加で利上げ。これ、けっこう大きなニュースです。
これによって、投資信託、企業型DC(確定拠出年金)、IDECOみたいな商品にも影響が出てきています。株価も動いたので、ちょっとドキドキした人もいるかもしれませんね。
まとめ:これからは「金利」とうまく付き合う時代
- 金利は経済の流れを調整する大事なツール
- 日銀が金利を操作して、物価や景気のバランスを取ってる
- 私たちの投資、ローン、年金にも金利は影響してくる
- これからは「金利を意識したお金の付き合い方」がポイント!
今までは「金利?関係ないし~」って思ってたかもしれませんが、これからは投資やお金の使い方を考えるうえで、金利ってめちゃくちゃ大事になります。
「なんとなく投資してる」から一歩進んで、「金利が上がりそうだからこうしてみよう」なんて判断ができると、もっと安心してお金のこと考えられるようになりますよ。
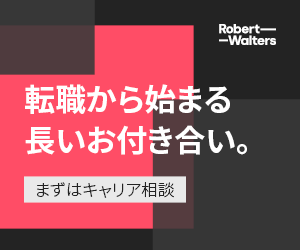





コメント