はじめに:グローバル企業と税金の問題
近年、世界の企業はグローバルに活動しています。日本に本社があっても、製造工場はタイ、販売拠点はアメリカ、ソフトウェア開発はインドで行っている、というのは珍しい話ではありません。
このような多国籍企業(国をまたいで活動する企業)にとって、各国で発生する利益にどれくらい税金がかかるのかは、とても重要な問題です。なぜなら、国によって法人税の税率が大きく異なるからです。
例えば、ある国では法人税が30%でも、別の国では10%ということがあります。企業としては、できるだけ税金の安い国に利益を集中させたいと考えるものです。これ自体は経済合理性にかなっていますが、過度な利益移転が行われると、税金を取り逃がす国(たとえば日本)にとっては大きな損失です。
そこで登場するのが移転価格税制です。
移転価格とは?
まず「移転価格」という言葉から説明します。
これは、同じグループ企業間で行う取引に使われる価格のことです。例えば、日本の親会社が海外の子会社に部品を輸出する場合、どの価格で売るのかをグループ内で決めます。このときの価格が「移転価格」です。
通常の企業間取引であれば、市場の競争によって価格は自然に決まります。しかし、親子会社など同じグループ内の取引では、価格を自由に設定できます。つまり、取引価格を操作することで、利益の出る場所(=税金を払う場所)を意図的に変えることが可能になります。
具体例で理解する移転価格
ここで簡単な例を見てみましょう。
- 日本に本社を置く「A社」は、税率30%
- シンガポールに子会社「B社」があり、税率10%
A社が原価100円の製品をB社に売るとします。
パターンA(正常な価格で売る場合)
A社 → B社に150円で売る
→ A社に利益50円(150円 – 100円)
→ この50円に対して、日本で法人税30%がかかる(税額15円)
パターンB(利益を移転する場合)
A社 → B社に原価と同じ100円で売る
→ A社の利益は0円
→ B社が製品を200円で売って、利益100円
→ この100円に対して、シンガポールで法人税10%(税額10円)
このように、売値(移転価格)を操作することで、税金の負担が大きく変わることになります。企業側は、なるべく税率の低い国に利益を移したくなるのです。
なぜ移転価格税制が必要なのか?
企業が自社グループ内で自由に価格を設定できることを悪用すれば、税金の少ない国にどんどん利益を移し、税率の高い国では赤字のように見せかけることも可能になります。
これに対して各国の税務当局は、「本当にそれは適正な価格なのか?」と問いただす必要があります。つまり、企業が内部取引に設定する価格が第三者同士の取引で使われる価格(=独立企業間価格)と比べて不自然に安すぎたり高すぎたりしていないかをチェックする制度が、移転価格税制です。
独立企業間価格(ALP: Arm’s Length Price)とは?
移転価格税制の中心となる考え方が「独立企業間価格(Arm’s Length Principle)」です。
これは、「企業グループ内の取引であっても、まるで独立した他人同士が取引しているかのような価格で行わなければならない」というルールです。要するに、親会社と子会社の間でも、市場での相場に基づいた価格で取引しなさい、ということです。
税務当局は、この考え方に基づいて企業の取引価格を精査します。そして、「あなたたちの移転価格は不自然であり、もっと高い(あるいは低い)価格であるべきだった」と判断すれば、その差額に対して追徴課税されることになります。
どのように価格を判断するのか?
では、どのように「適正な価格」=独立企業間価格を見つけるのでしょうか?
移転価格税制では、以下のような方法(算定手法)が用いられます:
独立価格比較法(Comparable Uncontrolled Price Method, CUP法)
同じような商品を第三者に売っている価格と比較します。
再販売価格基準法(Resale Price Method)
子会社が商品を販売する価格から逆算して、仕入れ価格を推定します。
原価基準法(Cost Plus Method)
商品の原価に一定のマークアップ(利益)を乗せて、適正価格を導きます。
利益分割法(Profit Split Method)
複数国の企業が共同で価値を生み出している場合、それぞれにどの程度の利益が妥当かを分け合う方法です。
取引単位営業利益法(Transactional Net Margin Method, TNMM)
営業利益率を第三者企業と比較し、異常に高すぎたり低すぎたりしていないかを分析します。
企業はこれらの方法を使って、自社の取引価格が「おかしくない」ことを示す書類(移転価格文書)を作成する必要があります。
日本における移転価格税制の制度
日本では、国税庁が移転価格税制を厳しく監視しています。特に、外国に子会社を持つ大企業は、毎年「ローカルファイル」と呼ばれる文書を作成し、税務調査に備えておく必要があります。
さらに、年間取引が一定金額を超える場合には、より詳細な「マスターファイル」「国別報告書(CbCレポート)」の提出も求められます。
BEPSと国際的な取り組み
移転価格は、日本だけでなく世界中で問題になっており、**OECD(経済協力開発機構)**が中心となって国際的なルール整備を進めています。
「BEPS(税源浸食と利益移転)」という国際プロジェクトでは、企業が税金の少ない国に利益を移しすぎないよう、各国が共通のルールを作っています。現在では、移転価格に関する文書化義務や報告制度は世界的な標準となりつつあります。
最近の傾向と実務上の注意点
かつては製造業中心でしたが、最近はIT企業やデジタル企業に対する移転価格のチェックが厳しくなっています。たとえば、ブランド価値やソフトウェア、ユーザーデータなど「目に見えない資産(無形資産)」にどれくらいの価値があるか、どう利益を分配すべきかという問題が注目されています。
また、移転価格は非常に専門的な分野であり、企業は税理士や国際税務のコンサルタントと連携しながら慎重に対応する必要があります。誤った移転価格を設定すれば、多額の追徴課税を受けるリスクがあります。
まとめ
移転価格税制は、グループ企業間の取引が適正な価格で行われているかをチェックし、過度な利益移転を防ぐための制度です。企業が税率の低い国に意図的に利益を移すのを防ぎ、各国が適正に税収を得られるようにするために、非常に重要な役割を果たしています。
企業にとっては、グローバル展開を行ううえで避けて通れない問題であり、事前の準備と綿密な価格設定が求められます。国際社会も協力してルールの統一を進めており、これからもますます重要性が高まっていく分野です。
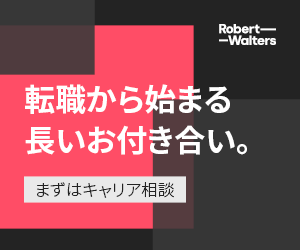





コメント