今回のテーマは「投資信託の純資産総額は大きい方が良いのか?」です。
投資信託を選ぶとき、「純資産総額」に注目しよう
投資信託を選ぶとき、確認しておきたい項目のひとつが「純資産総額」です。
これは、ファンドが持っている資産の合計から、手数料などの費用を引いたもの。つまり、「いまこのファンドには、どれだけの資産があるのか」がわかる数字です。
この純資産総額を知ることで、ファンドの規模や人気度、健全性などをチェックできます。この記事では、この金額が増減する理由や、それに伴うリスクについて解説します。
純資産総額が変動する3つの理由
純資産総額は、投資信託(ファンド)の「大きさ」を表す指標です。
私たちが売買する価格「基準価額」は、純資産総額を保有口数で割ったものから計算されます。
株や債券の価格変動
ファンドが持っている株式や債券の値段が日々変わるため、それに応じて純資産総額も増減します。値上がりすれば増え、値下がりすれば減ります。
投資家の売買(購入と解約)
ファンドを買う人が増えると、資金が入って純資産総額は増加します。反対に、解約が増えると資金が出ていき、純資産総額は減ります。
解約が続くとファンドの運用に悪影響を与えるため、安定して資金が入ってくるファンドのほうが安心感があります。
分配金の支払い
分配金とは、ファンドが得た利益の一部を投資家に分けるお金です。毎月分配型のファンドでは、そのたびに資金が出ていくので、純資産総額が減る要因になります。
分配金があると「資産運用している」という実感を得やすいですが、「分配金を出す=良いファンド」とは限らない点に注意しましょう。
純資産総額が大きいほど良い?そうとは限りません
「純資産総額が大きい=良いファンド」と思われがちですが、運用成績が良いとは限りません。
たとえば、投資対象が限られているファンド(小さな国やベンチャー企業など)では、資産が増えすぎると運用しづらくなることがあります。
「投資したくても対象がない」「希望の価格で売買できない」などの問題が出てくるのです。
そのため、運用会社はファンドの適正な規模を想定し、純資産総額や購入できる口数に上限を設けて調整しています。
また、資産が少なすぎるファンドは、採算が合わないとして途中で運用終了になることも。これを「繰上償還(くりあげしょうかん)」といいます。
もし運用中に繰上償還されてしまい、損失が出ていれば、そのまま元本割れ(損をする)になるリスクもあります。
繰上償還の条件は、ファンドの「目論見書(もくろみしょ)」や「運用報告書」に記載されているので、購入前に必ず確認しましょう。
まとめ:純資産総額は判断材料のひとつ
純資産総額は、ファンドの状況を知るための大事なヒントになりますが、「大きい=良い」とは限りません。
基準価額の変動以外にも、資金の出入りや分配金の有無など、さまざまな要因が関係しています。
投資信託を選ぶときは、純資産総額の動きにも注目しながら、自分の目的や運用方針に合っているかをしっかり確認してみましょう。
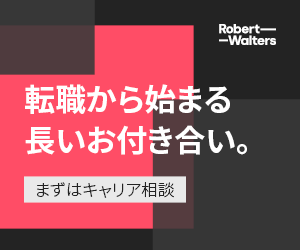





コメント