高校で「金融教育」が必修に!
2022年4月から、高校の家庭科で「金融経済教育」が必修になりました。
政府は、「これからの時代を生きるにはお金の知識が欠かせない」として、若いうちから金融リテラシー(金融の知識・判断力)を身につけることを重視しています。
また、2022年からは成人年齢も20歳から18歳に引き下げられ、クレジットカードやローンの契約も自分の判断で行えるようになりました。
つまり、お金の知識は高校生にも必須なのです。
金融庁の教材で学ぶ“お金の基本”
金融庁は、高校生向けにわかりやすい教材を公開しています。
この教材では、「家計管理」「貯める・増やす」「借りる」「備える」「金融トラブル」など、7つのテーマで体系的に金融を学べます。
社会人にも役立つ内容なので、「お金の基礎を学び直したい大人」にもおすすめです。
資産形成の基本:「収益性」「流動性」「安全性」
教材では、金融商品を選ぶ際に考えるべき3つのポイントが紹介されています。
| 観点 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 収益性 | どれくらい利益を得られるか | 株式は高め、預金は低め |
| 流動性 | 必要なときに現金化しやすいか | 普通預金は高い、保険は低い |
| 安全性 | 元本が減らないかどうか | 預金は高い、株式は低い |
💡 3つをすべて満たす金融商品は存在しません。
どこを重視するかを考えることが大切です。
投資に「リスクゼロ」はない!
教材の中にはクイズ形式の学習もあります。
Q:「確実に儲かる」「リスクがない」と言われた投資は安全?
答え:✕(間違い)
リスクが小さい投資はリターンも小さく、
逆に高いリターンを目指すならリスクも伴います。
「ローリスク・ハイリターン」は現実には存在しません。
📊 リスクとリターンの関係
低リスク → 利益小
高リスク → 利益大(ただし損する可能性も)
安定した資産づくりの3つの基本
教材では、リスクを抑えながら資産を増やす方法として
次の3つを紹介しています。
- 長期:時間を味方につけてコツコツ増やす
- 積立:定期的に一定額を投資する
- 分散:商品や地域を分けてリスクを分散する
この3つを組み合わせることで、着実な資産形成が可能になります。
NISA・iDeCoでお得に運用
実際に資産形成を始めるときに役立つ制度として、
教材では以下の2つが紹介されています。
- NISA(少額投資非課税制度):投資で得た利益が非課税
- iDeCo(個人型確定拠出年金):積み立てたお金が将来の年金に
どちらも税金の優遇を受けながら長期運用できる制度です。
体験できる「資産形成シミュレーター」
教材では、実際に自分の条件を入力してシミュレーションできる
「資産形成シミュレーター」も用意されています。
収入・支出・貯金額を入力すると、
どのようにお金が増えていくかをグラフで可視化できます。
→ コツコツ積み立てる効果(複利の力)を実感できるツールです。
※このシミュレーターは2025年12月末まで公開予定。
金融リテラシーは一生の財産
お金の知識は、投資だけでなく、
日々の買い物や契約、ライフプランの判断にも役立ちます。
高校で始まった金融教育は、
大人にとっても「学び直し」の良いチャンス。
金融庁の教材は、誰でもWEBから利用できます。
興味のある方はぜひチェックしてみてください。
💬 まとめ
- 高校で金融教育が必修化。若いうちからお金の知識が大切
- 「収益性」「流動性」「安全性」の3つのバランスがカギ
- 「長期・積立・分散」で安定した資産形成を
- NISA・iDeCoなどの制度を上手に活用
- 大人も学び直しに最適な教材が無料で利用できる!
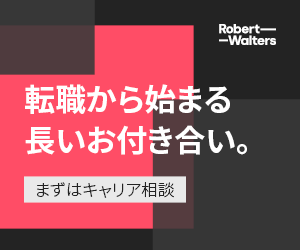





コメント