のれん償却とは?
のれん償却とは、企業の買収や合併(M&A)などで発生する「のれん」という資産の金額を、数年かけて少しずつ費用として処理していくことをいいます。
たとえば、買収した会社の中には、ブランドや顧客との関係、独自の技術など、目に見えない価値があります。この価値を「のれん」と呼び、買収金額がその会社の純資産より高い場合に発生します。
こののれんは「無形固定資産」として扱われ、毎年少しずつ「のれん償却」として費用計上し、価値を減らしていきます。償却する期間は最長で20年と決められています。
のれんとは何か?
M&Aで、ある会社が他の会社を買うとき、その支払金額が相手の「資産-負債(純資産)」を上回ることがあります。この差額部分が「のれん」です。
この差には、ブランド力や信頼性、販売ネットワーク、社員のノウハウなど、数字では測れない価値が含まれています。
償却期間はどれくらい?
日本の会計ルールでは、のれんは最長20年以内で償却する必要があります。実際には業界の慣習や会社の考え方に応じて、5年〜10年程度で設定する企業が多いです。
一度決めた償却期間は途中で変更できないため、慎重に決める必要があります。
のれん償却のメリット
① 突然の大きな損失を避けられる
のれんを毎年少しずつ償却していくことで、突然大きな損失(減損)が発生するのを防げます。特に景気の悪化などで企業の価値が急に下がった場合に備えた、安全なやり方です。
② のれんの実態に合わせた処理ができる
のれんは永遠に価値があるわけではないので、定期的に価値を減らすことで実態に合った会計処理ができます。
のれん償却のデメリット
利益が減って見える
償却することで、毎年の営業利益が減るため、企業の業績が悪く見えてしまうことがあります。特に買収後すぐに償却が始まると、買収効果が出る前に利益が下がってしまうこともあります。
実際の価値とずれることがある
企業の価値は常に変動しているため、毎年同じ金額を償却する方法だと、実際の変化とズレが生じる可能性もあります。
のれん償却の仕訳(会計処理)
たとえば、「のれん」が1,000,000円で、10年間で償却する場合、毎年の仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| のれん償却 | 100,000円 | のれん | 100,000円 | 1年目の定額償却 |
この費用は「販売費および一般管理費」に含まれるため、営業利益にも影響します。
7. 国際基準(IFRS)との違い
日本では「のれん」を一定期間で償却しますが、国際会計基準(IFRS)では償却せず、毎年「減損テスト」を行って、のれんの価値が下がっていないかを確認します。
つまり、IFRSではのれんの価値が下がったと判断されたときだけ、減損処理で一気に減らすのが特徴です。
8. 税務上の取り扱い
日本の税法では、会計上ののれん償却は法人税の計算では「損金」として扱われません。つまり、税金には影響しません。
ただし、事業譲渡や特定のスキームでM&Aをした場合は、税務上でものれんが発生し、「資産調整勘定」として5年間で月割り償却されます。これは会計とは異なる点なので注意が必要です。
9. のれん減損との違い
- のれん償却:あらかじめ決めた年数で、毎年一定額を費用として処理する。
- のれん減損:価値が下がったときに、その分を一気に減らす。
償却は計画的、減損は突発的。会計処理のタイミングと影響が大きく異なります。
10. 注意点とまとめ
のれんの償却は、M&Aの成果や企業の業績に大きな影響を与えるため、専門家の意見を交えた慎重な対応が求められます。
特に以下の点に注意が必要です:
- 償却期間は長すぎず短すぎず、現実的な設定にする。
- 償却による利益圧迫が、株価や資金調達に影響する可能性がある。
- 税務と会計の扱いが異なるため、両方の視点で検討する。
M&Aを考えている企業は、のれんの扱い方まで計画に含めておくことが重要です。
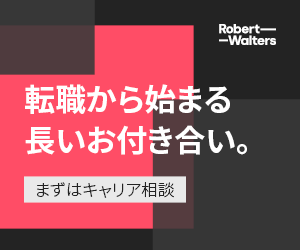





コメント